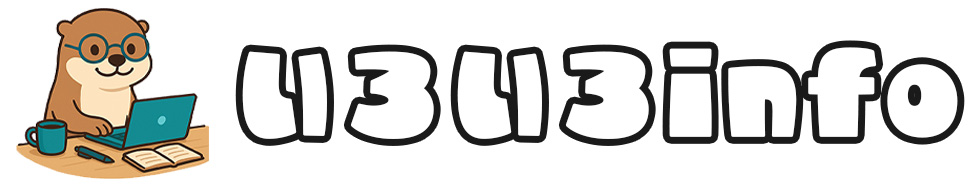画像引用元:DAIYA CASE
 男性
男性えっ…なかたに亭、もう閉店したん!?何かトラブルでもあったんかな…



そう思う方も多いようですが、実は閉店には中谷シェフのある想いが込められていたんです!
大阪・上本町で37年にわたり愛され続けた名店「なかたに亭」が、2024年3月に惜しまれつつ閉店しました。ファンにとって突然にも思えるこの出来事の裏には、店主の人生観や業界への深いメッセージが隠されています。
本記事では、閉店の真相とその後の展開、そして受け継がれる“なかたに亭スピリット”について詳しく解説します。
- なかたに亭が閉店した本当の理由
- 閉店後に広がる菓子業界への影響
- おすすめの後継スイーツや関連商品の紹介
なかたに亭閉店の理由は?
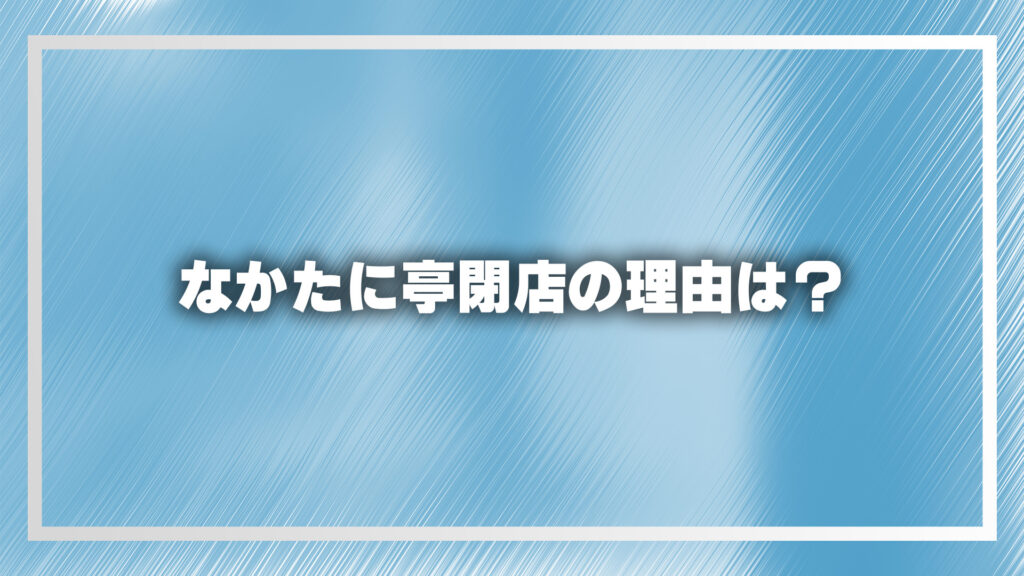
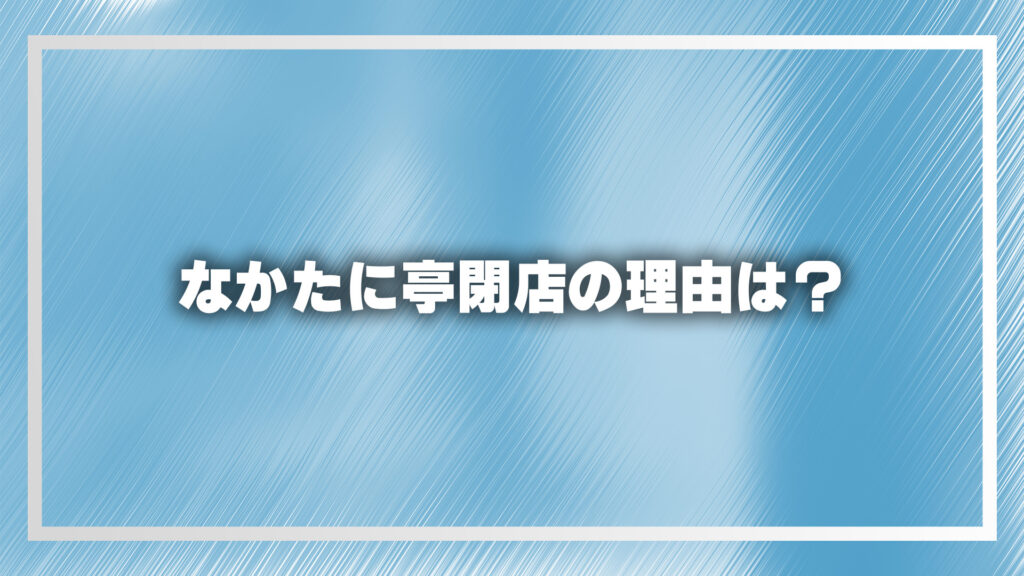
店主・中谷哲哉氏が選んだ「終わりの美学」
2024年3月、「なかたに亭」は惜しまれつつも37年の歴史に幕を下ろしました。閉店の理由について、オーナーシェフ中谷哲哉氏は「新しいことに挑戦したい」という前向きな動機を明かしています。
「65歳という年齢を迎えて、これまでにできなかったことをやってみたくなったんです」
出典:SAVVYインタビュー
閉店はネガティブな理由ではなく、「人生の次のステージへの移行」であることがはっきりと語られていました。これは“引退”ではなく、“転換”です。
閉店は突然の決断ではなかった
実際には数年前から閉店を意識していたことも判明しています。
- 店舗の老朽化
- 後継者の進路(奨太氏との役割分担)
- 長期的なキャリアプラン
これらを総合的に考え、2024年という区切りを選んだのです。
新しい挑戦と人生の価値観の変化
閉店理由の中で特に注目すべきなのが、「新しい体験を重ねることで得られる発見」を重視していたことです。
旅行がもたらした価値観の変化
中谷氏は閉店後、月に一度は国内を旅し、地域の食材や文化に触れるようになったと語ります。
「信州、九州など日本国内が今面白い! 生産地でいろんな食材や生産者さんに出合うのも楽しいです。」
出典:SAVVYインタビュー
この体験をきっかけに、地元の生産者と連携したお菓子作りへと関心が移っていきました。
クラシックからクラフトへ
かつての「フランス菓子の王道」を追求する姿勢から、現在は「クラフト(手仕事)の再定義」にシフト。
| 時期 | 主なスタイル | 主軸となる素材 | 菓子の位置づけ |
|---|---|---|---|
| なかたに亭時代 | フランス伝統菓子 | 輸入素材中心 | 技術・再現性 |
| 現在(YARD) | クラフトスイーツ | 国産素材・農産物 | 体験・物語性 |
このように中谷氏の中で「菓子=技術の表現」から「菓子=人と人をつなぐ手段」へと軸足が移ったことが閉店の核心にあります。
なかたに亭というブランドへの“誠実な別れ方”
閉店を決断するうえで、「ブランドの終わり方」にも深いこだわりがあったとされています。
全盛期に幕を下ろすという決断
日本の飲食店では「業績が落ちてから閉める」というケースも多い中、なかたに亭はあえて「愛されているうちに閉める」選択をしました。



こうした“美しい幕引き”ができるのは、店主の信念と覚悟があってこそですね!
ファンへの感謝を込めた最終営業
2024年3月17日、閉店日当日はなんと300人以上の行列ができ、2時間以上前から待機する人々の姿も。
- 開店前に用意していたケーキは即完売
- 最後のパフェには、リピーターも涙
- SNSでは「ありがとう、なかたに亭」の投稿が相次ぐ
このように、有終の美を飾った姿も「なかたに亭らしい」と多くの人々の心に刻まれました。
店主の言葉に見る「閉店」の哲学
“閉店”という選択を、店主・中谷哲哉氏は単なる終わりではなく、「これまでと違う自由な時間のスタート」と位置づけています。
「もう少し自由に動いて、見聞きしたことをお菓子で表現したい」
出典:SAVVYインタビュー
この言葉には、制約から解き放たれた中でこそ生まれる新たな創作意欲がにじみ出ています。閉じることでしか見えない世界がある。そんな静かな哲学を感じさせる姿勢です。



お店という枠を手放すことで、むしろ“表現の幅”が広がる。そんな逆説的な美学に心を打たれますね!
なかたに亭閉店後の影響と今後の展開
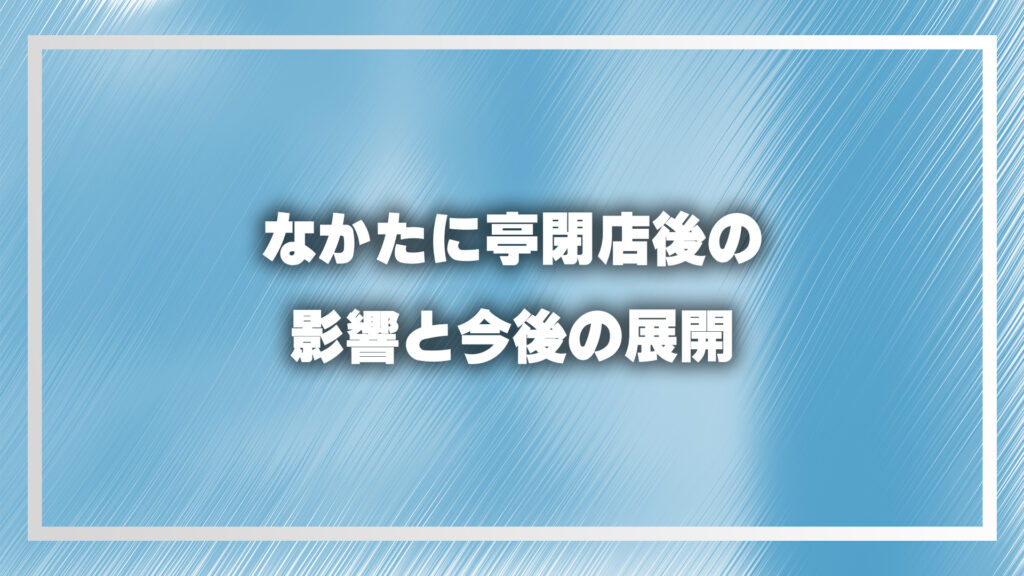
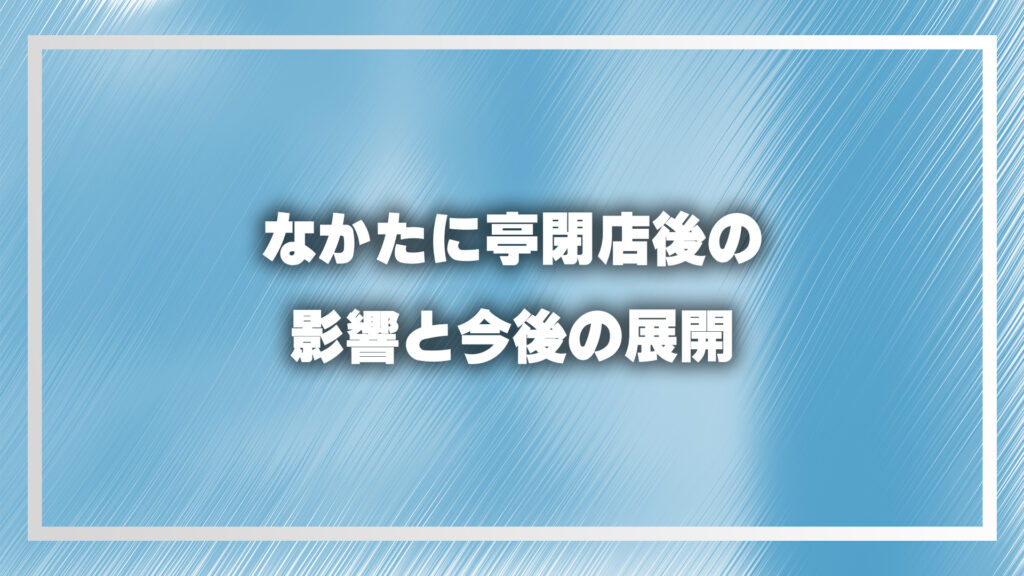
弟子たちが広げる「なかたに亭」の精神
なかたに亭の閉店は、パティスリー業界にも大きな余波をもたらしました。なぜなら、このお店で修業を積んだシェフたちが、現在の関西スイーツシーンを牽引しているからです。
なかたに亭出身の主なシェフと店舗一覧
| 名前 | 現在の店舗 | 特徴・スタイル |
|---|---|---|
| 廣瀬康一 | ケ・モンテベロ(大阪・福島) | フランス伝統菓子の技術を発展させた上品なケーキ。 |
| 西園誠一郎 | ラヴィルリエ(大阪・北浜) | 芸術的な造形と濃厚な味わいで有名。 |
| 吉川尚史 | プティ・ラパン(大阪・南森町) | 地元に根ざした素材重視の小規模店。 |
こうした弟子たちが築く店舗には、「素材を尊重し、丁寧に仕上げる」というなかたに亭の哲学が確かに継承されています。
「YARD」で続く菓子づくりの新境地
閉店後も、中谷哲哉氏は第一線を退いたわけではありません。大阪・空堀で営まれる「YARD Coffee & Craft Chocolate」は、なかたに亭の精神を新しい形で体現する場所となっています。
YARDの特徴と提供スタイル
- 自家焙煎のスペシャルティコーヒー
- カカオ豆からチョコレートを製造(Bean to Bar)
- 地元の素材を活かした焼き菓子とスイーツ
- 息子・中谷奨太氏と共同経営
YARDでは、なかたに亭時代にはなかった「お菓子+飲料」の空間演出を重視しており、“カフェで味わう高品質菓子”という新たな提案をしています。



素材と向き合う姿勢、クラフト的な発想は、確かに進化を遂げています!
YARDのチョコレートは公式サイトで購入可能です。
気になる方はぜひこちらからチェックしてみてください!
閉店後のファンの動きと需要の高まり
なかたに亭が閉店したことによって、ファンの間では“幻のスイーツ化”が起きています。特にSNS上では以下のような反応が目立ちました。
SNS上での反応傾向(X・Instagramより)
| 傾向 | 内容の例 |
|---|---|
| 思い出の共有 | 「大学時代、毎週通ったなかたに亭が閉店…泣ける」 |
| 写真の投稿 | パフェ・オペラなど代表メニューの写真と共に投稿 |
| 現在の商品を探す声 | 「なかたに亭のケーキを再現できるレシピはないの?」 |
こうしたファンの投稿は、閉店の衝撃が一過性のものではなく、長く記憶され続けるものだと証明しています。
また、Google検索のサジェストでも「なかたに亭 再開」「なかたに亭 レシピ」といったキーワードが浮上しており、継続的な需要があることが読み取れます。
菓子業界に与えた影響と評価の変化
なかたに亭の閉店は、単なる一店舗の終焉ではなく、業界全体に“節目”をもたらしました。
メディアでの扱いの変化
| メディア | 閉店報道 | 閉店後の企画 |
|---|---|---|
| MBS毎日放送 | 「300人超の行列」 | 閉店後の密着企画を放映 |
| SAVVY(京阪神Lマガジン) | インタビュー掲載 | その後のYARDも特集 |
| 朝日新聞デジタル | 社会面で報道 | 食文化コラムでの再登場 |
一般紙やテレビが報じるというのは、パティスリー業界では非常に珍しく、それだけ地域・業界に根差していた証です。
菓子業界の変化への“刺激”
- 独立志望の若手が増加
- 地方素材への注目度が高まる
- クラフト系スイーツの人気拡大
なかたに亭のような老舗が「技術の象徴」から「価値観の転換点」として語られるようになったことは、業界そのもののあり方をも見直す契機になったといえるでしょう。
まとめ|なかたに亭 閉店の理由は?37年の歴史に幕を下ろした背景とは
なかたに亭が37年の歴史に幕を下ろした背景には、店主・中谷哲哉氏の「これまでにできなかったことをしたい」という前向きな意志がありました。65歳という節目での決断は、“終わり”ではなく“新たな始まり”として捉えられており、閉店後もその哲学はYARDや弟子たちの店舗に確かに受け継がれています。
また、閉店の影響はファンの間だけでなく、菓子業界全体にも波及。クラフトスイーツや素材重視の流れを加速させるきっかけにもなりました。地域の食材や人との関わりを大切にするスタイルへと転換する中谷氏の姿勢は、これからの菓子づくりにおける新しい指針となりつつあります。
「なかたに亭」の閉店は、惜しまれながらも、次のステージへの希望を感じさせる“美しい幕引き”だったと言えるでしょう。
2400 – 3